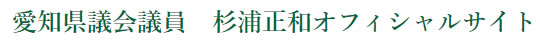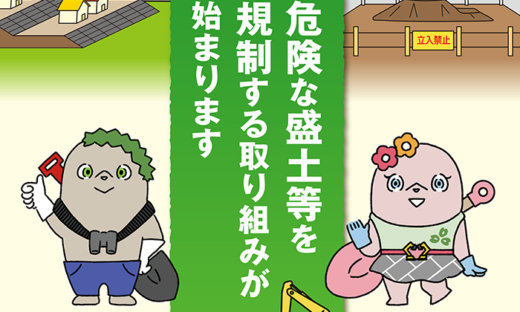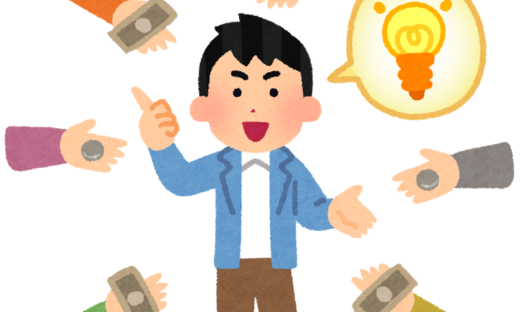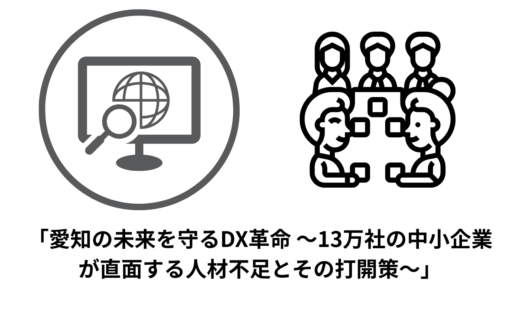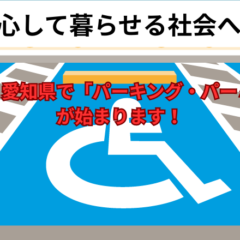持続可能な農業の実現に向けて─「家」から「経営」へ、転換の時

日本の農業が今、大きな岐路に立たされています。農業従事者の高齢化と後継者不足が深刻化するなかで、「農家が農家の子に継がれる」構造が限界を迎えつつあるのです。
📉 農業人口、2030年に約76万人へ
農林水産省統計によれば、2020年時点で基幹的農業従事者は136万人、そのうち約7割が65歳以上です。
財務省の推計では、2030年には76万人程度にまで減少すると見込まれています。
これは、わずか10年で約40%以上が離農または引退することを意味します。
愛知県でも、農業の中核を担う方々の多くが高齢であり、この「人がいない」という構造的問題に目を背けてはなりません。
私自身、農業に関わってきた者として、現場の苦労を身をもって知っています。だからこそ、私は「家族単位の農家を守ること」と「農業を産業として持続させること」は、もはや別次元の課題として捉えるべきだと考えています。
🧮 継承確率の現実──13人に1人しか継がれない?
農家の子が結婚し、平均出生数(1.25人前後)を前提に、そのうち1人が農業を継ぐと仮定して試算すると、次世代への農業継承率は約7.8%、つまり13人に1人にすぎません。
もちろんこれは単純化したモデルですが、現実として農家戸数を維持し続けることは極めて困難であることを示しています。
✅ 前提の整理:個人農家 vs 農業法人の違い
| 要素 | 個人農家 | 農業法人(雇用型) |
|---|---|---|
| 後継者の出自 | 主に実子・親族 | 雇用者・外部人材(親族でなくても可) |
| 継承方法 | 家業の継承 | 経営の引き継ぎ(法人継続) |
| 継承の条件 | 子が継ぐ意志・能力 | 後継候補の採用・育成・登用 |
| 確率に影響 | 結婚・出生・職業選択 | 雇用条件・育成制度・法人の魅力 |
| 継承の柔軟性 | 低い | 高い(非血縁者でもOK) |
この違いが、将来の農業の形を決定づけます。
🧩 法人化こそ、農業の持続可能性を高める道
6月議会で私は、農業の法人化支援と人材育成基盤の強化について県に質問を行いました。
現在、愛知県では非農家出身の新規就農者が全体の6割以上を占めており、これは農業が「家業」から「社会に開かれた産業」へと変わり始めている証です。
法人経営体は、地域雇用の受け皿として新規就農者を迎え入れ、教育・雇用・技術継承を「仕組み」で行うことができます。
単なる“家の継承”ではなく、“経営の継承”へと軸足を移す時なのです。
✅ モデルの構築:農業法人が1世代(約25年)継続する確率
農業法人が「1世代分」事業継続し、後継者を確保して存続する確率を、次のような要素の仮定で表すことができます:
-
A. 法人が25年後も存続する確率 … 約60〜70%
-
B. 後継者候補を雇用できる確率 … 約80%
-
C. 後継候補が定着する確率 … 約40〜50%
-
D. 経営幹部に育つ確率 … 約20〜30%
計算式:
P(法人継承) = A × B × C × D
平均値で計算すると:
0.65 × 0.80 × 0.45 × 0.25 ≒ 0.059(約5.9%)
👉 個人農家の推計(約7.8%)と数値上は近いものの、法人には「母数を増やせる」強みがあります。
1回の失敗で終わる個人農家に対し、法人は雇用を通じて複数回の挑戦が可能であり、長期的には法人の方が持続性は高いと考えられます。
🧓 終活と継承──引退ではなく「つなぐ」仕組みを
高齢農業者の「辞め時がわからない」「農地をどうしたらいいかわからない」という声に、現場はあふれています。
私は「農業終活」の支援が不可欠だと訴えました。農地や機械の承継先を整理する「終活ノート」の導入や、農業資産の移譲を専門的にサポートする相談体制の整備など、引退と継承の「つなぎ」を制度化すべきです。
また、高齢者が持つ経験と技術を新規就農者に伝える「指導役」的な活躍の場も、人生の第二章として創出すべきと考えています。
🎓 経営教育の強化──農業を担う“次の世代”のために
農業を単なる生産活動ではなく、企業経営と同様に捉える感覚が必要です。そこで私は、農業高校における実践的な農業経営教育の強化を提案しました。
損益分岐点や人材管理、法人設立や資金繰りといったリアルな知識を、高校段階から学ぶことができれば、将来の経営者が生まれやすくなります。
🔁 「人材循環」が農業を救う
現代の農業は、「血縁」ではなく「志縁」によって支えられていくべきです。
農家出身者も、そうでない人も、農業に関心のある人材が地域に入り、学び、働き、継承していく。そんな「人材循環」を実現することこそ、食料安全保障の基盤を築く道です。
📣 おわりに──農業は変わる。だから政治も変わる。
農家の戸数をただ守るのではなく、農業を未来につなげるための経営体をいかに支援するか。
これは、愛知県の農業政策が根本的に問い直されるべき局面に来ていることを意味します。
農業が「家」ではなく「産業」として、持続可能な形で地域に根を張っていく──
そのために、私はこれからも議会で声を上げてまいります。