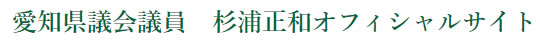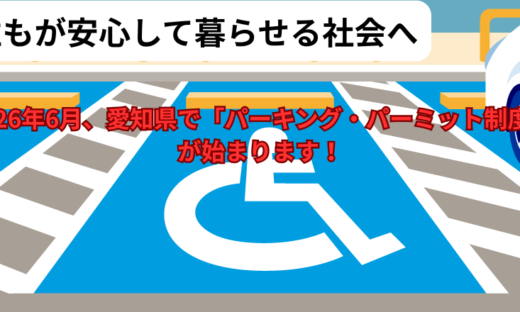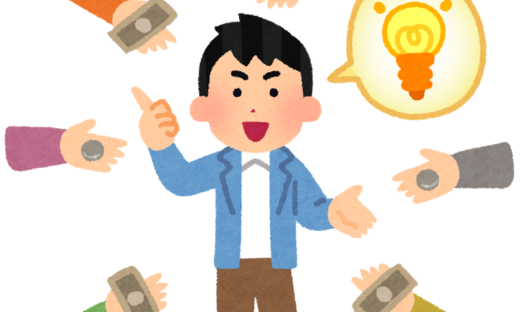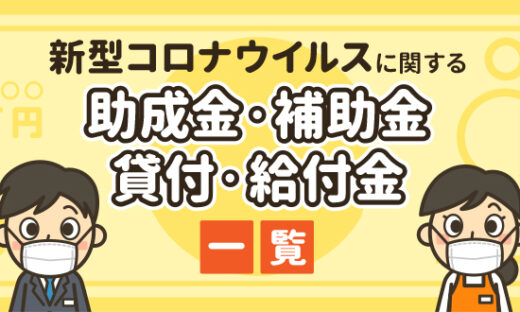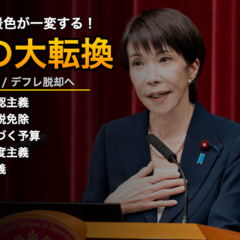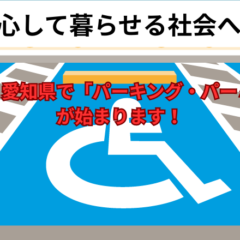障がい者の運転免許取得支援 ~移動の自由を全ての人に~

障害があっても、誰もが自由に移動できる社会。それは決して夢物語ではありません。今回は、この実現に向けた私の取り組みについてご報告させていただきます。
■心を動かされた出会い
ある日、切実な表情で私の事務所を訪れたお母様の話が、私の目を開かせてくれました。小人症の息子さんの運転免許取得についてのご相談でした。息子さんは当初、手動式での運転免許を取得。しかし後になって、実は延長ペダルでも運転可能だったことが分かったのです。
手動式の改造費用は約30万円。一方、延長ペダルならわずか5~6万円。この大きな差額に、お母様は「もっと早く知っていれば…」と悔しそうに話されました。この言葉が、私に行政の縦割りの壁を痛感させました。
■衝撃的な現状
愛知県の人口約750万人、そのうち障害者手帳をお持ちの方は約40万人。しかし、障害者の方の運転免許取得者数は驚くほど少ないのです。
・令和5年:57人(うち手動式は6人)
・令和4年:46人
・令和3年:44人
なぜこれほど少ないのか。実態を知るため、私は県内の自動車改造部品会社や教習所を直接訪問しました。
■現場の声から見えた課題
1. 教習所の厳しい現実
・県内48校中、障害者対応可能な教習所はわずか16校
・手動式車両保有は9校のみ
「障害者用の設備投資、専門知識を持つ指導員の確保…すべてが大きな負担です。でも、誰かがやらなければ」という教習所の声が胸に響きました。
2. 改造部品会社の奮闘
驚くほど進化した最新の運転補助装置。「障害があっても、乗りたい車に乗れる社会を」と情熱を持って開発に取り組む企業の姿に感銘を受けました。しかし、教習所への無償提供を続ける負担は大きく、このままでは限界があります。
■動き出した行政
私の一般質問を受け、変化の兆しが見え始めています。
・県警本部:運転補助装置についての知識を深め、適性判断の柔軟化を推進
・福祉局:
– 48市町で運転免許取得費用の助成制度を実施
– 教習所の環境改善に向けた本格調査を開始
– 障害者対応可能な教習所を増やすための新たな方策を研究
■具体的な提案
しかし、まだ課題は残されています。私は以下の取り組みを提言しています:
1. 教習所支援の強化
・障害者用設備への補助金制度の創設
・改造部品企業と教習所のマッチングシステムの構築
・専門指導員育成プログラムの開発支援
2. 包括的な支援体制の確立
・後天的障害者への支援制度の創設
・市町村間での支援格差の解消
・ワンストップ相談窓口の設置
障害があっても、自分の意思で行きたい場所に行ける。働きたい場所で働ける。それは、すべての人に与えられるべき当たり前の権利ではないでしょうか。
一人一人の「できる」を支援する。それが私たちの使命です。